T.S.
研究開発センター 素材・技術開発室
工学府 応用化学専攻 修了
2011年入社
 RECRUITING
RECRUITING 「人と地球に“やさしく、あったかい”」を経営理念とするニッケグループが、新規事業として力を入れているのがメディカル関連分野。新薬の開発において早期に副作用を発見する独自の評価技術の実用化に向けて、研究開発センターで働く社員たちの懸命な努力が続けられている。

研究開発センター 素材・技術開発室
工学府 応用化学専攻 修了
2011年入社
入社後、研究開発センターに配属され、共同研究先の博士後期課程に進学。専門的な知識習得を契機に、繊維加工技術を活用したメディカル用資材の開発を手掛けている。

研究開発センター 素材・技術開発室
工学研究科 ファイバーアメニティ工学専攻 修了
2017年入社
キャリア採用で入社し、ナノファイバーの利用方法の検討やゼラチンを用いた培養基材の開発を担当。現在は主にメディカル素材開発の計画立案や進捗管理を行っている。

研究開発センター 素材・技術開発室
理学系研究科 生物科学コース 修了
2019年入社
入社後、素材・技術開発室に配属され、ゼラチン繊維の品質安定化や製造の標準化に注力。現在その一環として、ゼラチン繊維の製造や品質改善等を進めている。

研究開発センター システム技術・環境開発室
理学研究科 化学専攻 修了
2018年入社
入社後、素材・技術開発室に配属され、生体吸収性メディカル用資材やゼラチン繊維の開発に従事。現部署に異動後、ニッケグループのDX推進等に取り組んでいる。
STORY.01
新薬の開発過程は複雑で、長期間にわたり高額な投資が必要とされる。中でも、開発の終盤で予期せぬ重大な副作用が明らかになり、新薬の開発中止につながることも少なくない。こうした背景から、製薬企業は開発の初期段階での副作用の検出に注力している。当社が開発に取り組んでいるのは、新薬の創出ではなく、既存および開発中の薬の安全性を効率良く検証するための技術である。これは独自の繊維加工技術により作られたゼラチン繊維と、ヒトiPS細胞由来の細胞を使用しており、開発中の薬がヒトの体に及ぼす副作用を、より現実に近いモデルで迅速に検出することを可能にする。
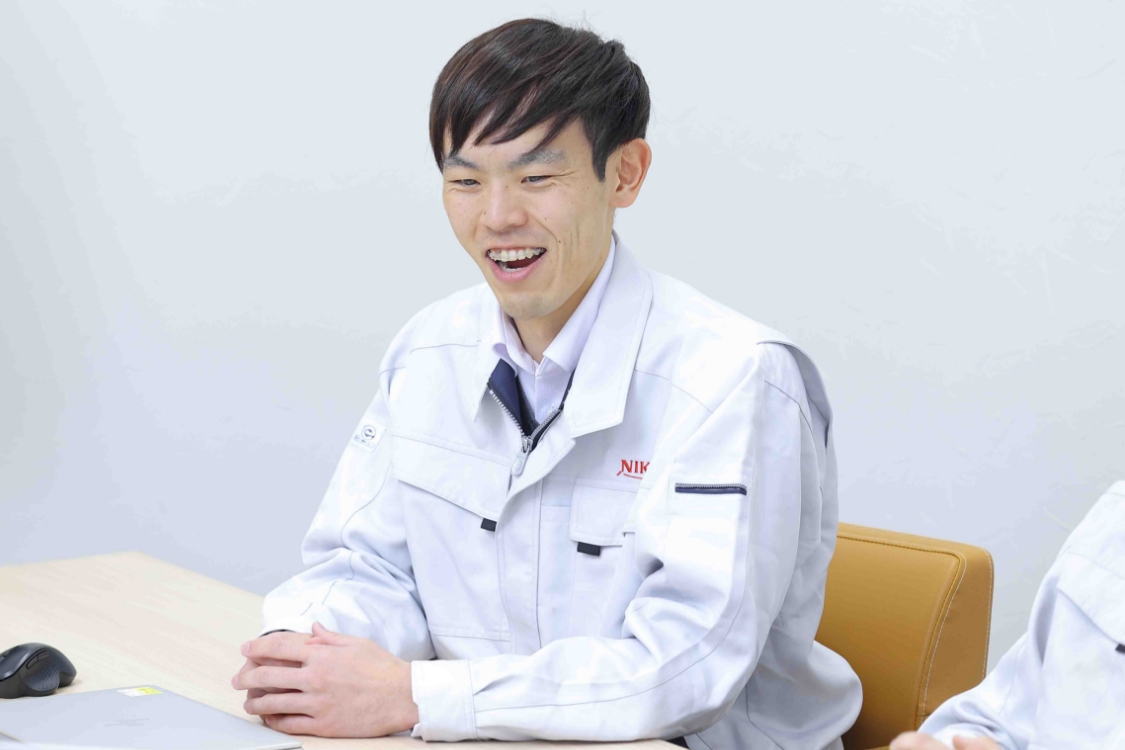
「ニッケが先行発売した細胞培養用のゼラチン繊維は、ヒトの体にとても親和性が高く、再生医療用途への開発を進めてきました。しかし再生医療分野での実用化までには非常に長い時間を要するため、“新薬の開発に役立てることで、少しでも早く社会に貢献できないか”と考えたのが今回のプロジェクトの発端です」そう話すのは、プロジェクト全体の牽引役を担うT.S.である。
ニッケにとって製薬分野はまったくの異業種であり、自社史上初の試みとなる。T.S.は薬の評価技術と知識習得のために大学に駐在するとともに、様々な製薬企業へ開発課題のヒアリングを開始。同時に確かなビジネスへ育て上げるためのプラン構築と製品価値の確立を目指して奔走し始めた。

STORY.02
製薬企業では、iPS細胞を使って新薬の開発を進める試みが進んでいた。その中で、iPS由来の心筋細胞を培養して作った心臓のモデルでは、ヒトの心臓のように大きく収縮しないことが課題であった。これを解決するために、T.S.はニッケで開発したゼラチン繊維を活用しようと考え、繊維加工に豊富な知見を有するN.S.に委ねた。
「ゼラチン繊維は、製造する条件によって繊維の太さや硬さが大きく変わってしまいます。心筋細胞に適したゼラチン繊維を作り上げるのに、試作品を何度も作っては評価を繰り返しました。心臓に近い機能を満たすことは非常に難しく、ニーズを満たすものを完成させるまでに1年はかかったと思います」(N.S.)

N.S.がベースを作ったゼラチン繊維を、製品として製薬企業に使用してもらうには、品質を一定に保つ必要がある。ゼラチンは温度や湿度の影響を受けやすい特性があり、顧客の使用環境によって形状等が変化する可能性もあった。こうした点を解消し、品質を安定化させる工程に、Y.T.が力を注いだ。
「特に大変だったのが、完成品としての基準を決めることです。ゼラチン繊維の製造から、心筋細胞で問題がないことを検証するまでの工程は、2カ月以上もの期間がかかり、開発スピードを大幅に遅らせる要因となるため、大いに頭を悩ませました。最終的に、あらゆる条件を掛け合わせたサンプルを大量に用意して、同時に比較実験することで基準を決定しました。研究開発は根性も必要です(笑)」(Y.T.)
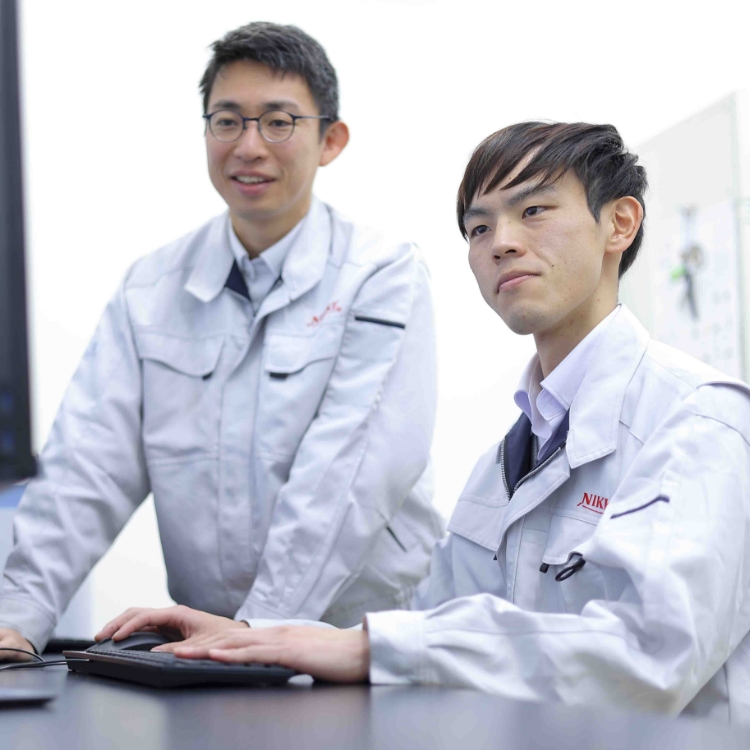
こうして心筋細胞に適したゼラチン繊維は完成したが、培養容器に入れて使用するにあたり、試作段階では手作業で容器に移していた。しかしゼラチン繊維は直径数ミリの小さな丸い形状で、試験のたびその一つずつを容器に並べていては非効率極まりない。そこで、ゼラチン繊維を培養容器にセットする工程の自動化を考案し、尽力したのがY.N.だ。
「最も困難だったのは、手作業で行っていた製造のコツを標準化し、自動化することです。自動機開発の初期段階ではコツの再現が上手くできず、期待する心筋細胞の機能が得られませんでした。コツの課題解決は秘密なので詳しく言えませんが、随分苦労しました。培養基材の開発も自動機の開発もすべてが初めての経験だったので、周りの方の協力を得てどうにか製造条件を決めることができました」(Y.N.)
STORY.03
プロジェクトスタートから約5年。T.S.以下メンバー4人が製品化した新薬開発用のゼラチン繊維は今、開発協力を得た製薬企業を含め、多数のお客様に提供するフェーズに至っている。各メンバーが異分野に挑み、それぞれに立ちはだかった課題を乗り越えた成果が、ニッケの新しいメディカル事業として花開こうとしている。
チーム一丸でメディカル事業の飛躍へ向かってさらなるチャレンジを続けようとする意気込みを、T.S.が代表して次のように語った。

「ニッケは間もなく創業130周年を迎えます。今後さらに発展してゆくために、新規事業や新たなビジネスモデルの構築が不可欠と考えています。メディカル分野は事業発足からまだ歴史が浅いとはいえ、間違いなく事業の柱の一つに成長してゆくと私は確信しています。また、お客様も疾病に悩む患者さんも幸せにできる、夢のある取り組みです。これからも今回のプロジェクト同様のチームワークを発揮することで、ニッケのメディカル事業の成長を支えて社会に広く貢献できるよう、一層努力していきます」
